


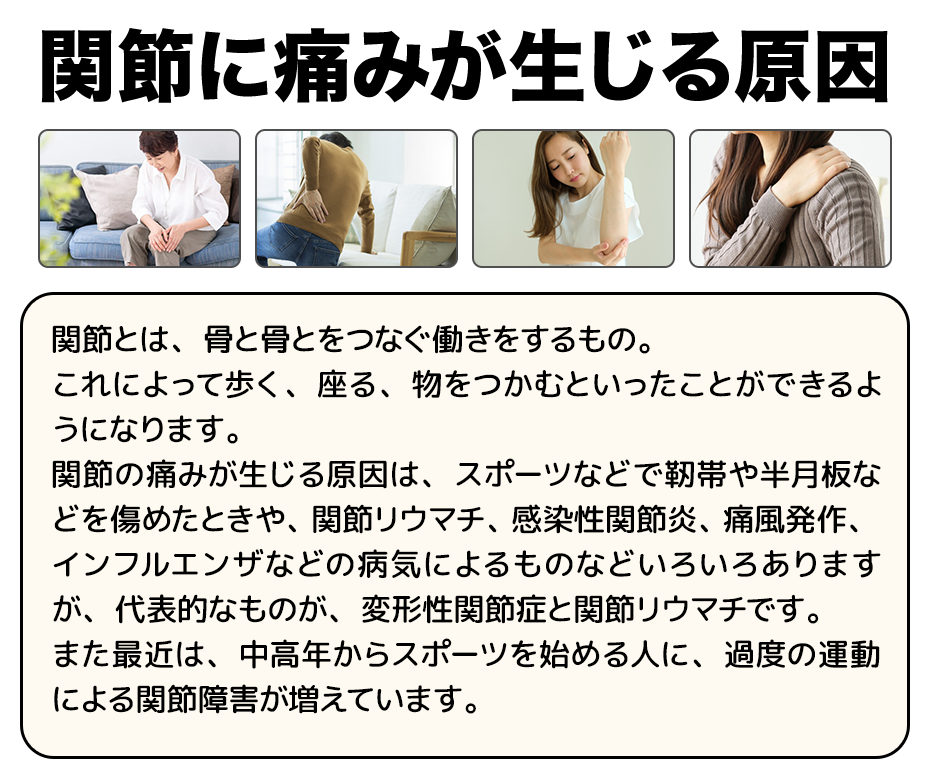
野球やテニス、陸上競技などのスポーツにより、筋肉や腱(けん)、靭帯(じんたい)に過度な負担が加わって、慢性の痛みを生じる疾患がスポーツ障害です。スポーツ障害では、症状が出現している場所に炎症や痛み、腫れなどが生じます。
スポーツ障害は柔軟性の低下や不十分な筋力、ケア不足による疲労の蓄積などが原因で発生します。痛みや動かしにくさとうまく付き合いながら運動できるものもありますが、場合によっては運動を中止しなければならないこともあるため、医師と相談することが大切です。
スポーツ障害が起こる原因はさまざまですが、体の使い過ぎによる柔軟性の欠如、もしくは過度の柔軟性、栄養や休養の不足とそれに伴う免疫力の低下、間違ったフォームなどが考えられます。早期の回復を目指すには、十分な睡眠や休養、栄養をとり、適度な柔軟性を確保することが大切です。
筋肉の緊張をほぐして血流を改善し、痛みのもととなる物質を取り除く効果も期待できます。
運動前のストレッチには、運動に適した体の準備のために、腕や足などの身体のさまざまな部分を回したり、動かしたりとする運動を。柔軟性の改善や筋肉の緊張緩和、血流促進、ケガ予防などの効果があります。
一方、運動後のストレッチには、運動によって興奮状態にある神経を落ち着かせ、疲労物質の代謝を促す効果や、緊張した筋肉をリラックスさせる働きがあります。
筋力を高めることで、身体にかかる負荷を軽減できます。
スポーツなどで繰り返し負荷がかかりやすい箇所やその周辺の筋肉を鍛え体幹を強化しましょう。再発防止にもつながります。
スポーツ障害の予防と回復のためには、毎日の食事が大切です。
身体を作る基本となる三大栄養素(炭水化物、脂質、たんぱく質)をしっかりとるとともに、疲労回復を高めて筋肉や腱のダメージを抑えるビタミンやミネラルが不足しないようバランスのよい食事を心がけ、日々の疲れを残さないために食事の仕方を考えてみましょう。

「スポーツ障害の予防と回復のためには、毎日の食事が大切」ですが、生活環境の変化や体の機能低下により、シニア世代は食が細くなるとされています。
そこで、手軽に摂取できるプロテインは、食事量が減少した際の栄養素を補給する手段としても活用できます。
プロテインを摂るメリットは、手軽にたんぱく質を摂取できることです。
たんぱく質は内臓や皮膚、血液、髪の毛などを作るのに必要不可欠な栄養素です。
現在、シニア世代の多くがタンパク質不足だといわれています。特に運動量の多い人は、エネルギーだけでなくタンパク質も圧倒的に不足しているため、プロテインを活用して補うようにしましょう。
特に、たんぱく質不足に陥りやすい食欲低下や食事制限をしている方に向いており、ドリンクなどで気軽にたんぱく質を摂取できます。
50歳前後からは消化酵素の活性が急激に低下するため、若い頃よりも積極的にタンパク質を摂取しなければ、筋肉量がどんどん減少してしまいます。
健康寿命を縮める要、フレイルア(要介護手前の虚弱状態)やサルコペニア(加齢による筋力低下)のリスクを高めないためにも、50代からは栄養の取り方を考え直しましょう。
高齢者が安心して利用できるプロテインは、吸収の良さや飲みやすさ、栄養バランスが重要なポイントです。プロテインは、商品によって含まれている成分や含有量が異なります。
ご自分の目的やライフスタイルに合った商品を選んでみてください。含まれる栄養が少なければ十分に栄養補給しにくく、多すぎれば健康被害の要因になりかねません。求める栄養が適度に含まれた最適なプロテインを選びましょう。
タンパク質の1日の摂取目標量は、身体活動レベルがふつうの前期高齢者男性で90~120g、活動レベルが低い後期高齢者女性で53~70gです。(参考:厚生労働省)
タンパク質に耐容上限量は設定されておらず、通常の摂取範囲でデメリットは少ないといえますが、タンパク質を過剰摂取すると腎臓や肝臓にかかる負担が大きくなってしまいます。腎臓や肝臓への負担を考慮し、持病を持っている人はプロテインの使用前に主治医に相談してください。
関節リウマチとは、免疫の異常により関節に炎症が起こり、関節の痛みや腫れが生じる病気です。関節がダメージを受けて壊れていくため、治療なしでは、ほとんどの場合、慢性に進行していきます。
関節リウマチは女性に多い病気で、以前は40歳代で好発することが多いといわれていますが、高齢化が進むにつれて近年では60歳代以上で発症する方が増えています。
また、高齢発症関節リウマチは女性よりも男性に多いという特徴があります。
発症のきっかけは、細菌・ウイルス感染、過労、ストレス、妊娠・出産、喫煙などがきっかけになることが多いとされていますが、高齢発症関節リウマチは加齢による免疫機能の変化(免疫老化)が考えられています。
関節リウマチかどうかを判断することは容易ではありませんが、関節症状がある、リウマチが心配、という時は、早めにリウマチ専門医に相談することをお勧めします。
治療は薬を使った治療 (薬物療法) を中心に、リハビリテーション、手術などを、必要に応じて組み合わせて治療を行うのが一般的です。早期の治療が大切で、病気の進行を抑え、痛みを取り除くことが目標です。
関節リウマチは、一生治らない病気ではありません。完治は難しいですが、適切な治療によって日常生活に支障がない状態を目指すことができます。
変形性関節症は関節の軟骨がすり減って骨の形が変わってしまう病気です。
関節のある場所すべてで発症する可能性があり、なかでも多い部位は、親指の付け根の関節、指の第一関節、膝、股関節です。
症状としては、関節の痛みや腫れ(腫脹)、関節水腫(関節に水分がたまる状態)を起こし、関節の変形や可動域制限(動く範囲が狭くなること)などにより、関節の機能障害が起こります。関節の痛みと機能障害の程度によっては健康寿命にも影響してきます。
軟骨は、関節が滑らかに動くのを助け、骨と骨の間で衝撃を吸収するクッションのような役割を果たしています。健康な関節では、軟骨が骨の末端を覆っていますが、変形性関節症になると、この軟骨がダメージを受けてすり減り、その結果、関節に痛みとこわばりが現れます。
このため、変形性関節症は、「経年劣化」による関節炎だと言われています。
しかし、ひざの軟骨がすり減った高齢者だけの問題ではありません。変形性関節症は65歳以上に多く見られますが、どの年齢にも起こり得ます。
一般的には、45歳ぐらいから症状が現れ始めるとされています。
変形性関節症の主な症状は、関節周囲の痛み、腫れ、違和感、引っ掛かり感です。
ただし、部位によって症状が異なるものもあります。
膝の痛みと関節炎の症状で膝に水がたまることが主な症状です。
変形性膝関節症は、変形性関節症の中でもっとも多く、「年をとって膝が痛い」という場合のほとんどがこの病気です。女性に起こることが多く、ほとんどがO脚変形を伴い、内側の関節面の軟骨が擦り減るように進んでいきます。
はじめは立ち上がるときや歩き始めるときなどの動作開始時に痛みが生じ、通常は休むと痛みがなくなります。
関節の変形が進行すると、膝の内側が痛み、階段の上り下りや正座、膝の曲げ伸ばしが難しくなり歩行が困難となるほか、安静にして足を動かさないようにしていても痛みに襲われるようになります。
肘を動かすと痛みが出て、安静にすると軽減します。症状が進むと安静時にも痛みを感じることがあります。
進行すると骨棘(こつきょく)と呼ばれる骨の棘があらわれ、肘の動きが悪くなり、日常生活の動作でも痛みを感じるようになり、関節の動きが制限されて、口に手が届かないなど日常生活上の動作に支障が出ます。
さらに進行すると肘関節の痛み、動きの制限、小指と薬指のしびれといった症状が現れることもあります。また、頻度は低いですが、肘にも変形性関節症が生じることがあります。
変形性脊椎症の多くは軽症の場合自覚症状がありません。変形が進むと慢性的な痛みが生じたり関節の可動域が制限されたりします。
変形部位によって症状は異なりますが、頚椎が変形した場合には、腕や手の痛み、しびれがみられることもあります。数年にわたって徐々に進むことが一般的ですが、外傷が原因で急激に症状が現れることもあります。

残念ながら、すり減った軟骨や、変形を元に戻すことはできません。
症状の悪化を予防するためには、関節に余計な負荷をかけぬよう、日常生活を気をつけることが大切です。病院での治療を早く始めるとともに、生活習慣の見直しによって、できるだけ進行を遅らせることが重要です。
変形性関節症で関節が痛むと、あらゆる動作が困難になりますが、休みすぎるとかえって症状を悪化させる可能性があります。
穏やかな運動は関節機能にとって重要であり、痛みと動きの制限という変形性関節症の悪循環を防ぐのに役立ちます。ヨガや水泳など関節に優しいスポーツが適しています。変形性関節症の場合、積極的に関節を安定させるために筋肉を発達させることも重要です。
変形性関節症のリスク要因の1つは太りすぎです。体重が増えると関節に大きな負担がかかるからです。肥満の方では、減量することで変形性膝関節症や変形性股関節症の症状が改善します。
下肢の関節に痛みがあると、運動量が減り、そのためさらに体重が増えるという、悪循環に陥りがちです。意識して体重をコントロールしましょう。
しかし、関節に負担をかけるのは体重だけではありません。
もう1つの原因は、太りすぎの人は一般的に活動性が低い傾向があり、関節に十分な栄養が供給されないことです。さらに、筋肉が十分に発達していないため関節を適切にサポートできません。
減量と的を絞った運動は、変形性関節症患者の関節の健康に良い影響を与えます。負担が軽減され、関節機能が改善され、安定筋が刺激されて強化され、代謝プロセスが促進され、痛みが軽減されます。
変形性膝関節症の痛みには、保温が大切です。膝が冷えてしまうと血流が滞り、痛みを感じやすくなります。骨折や靭帯損傷などの怪我をした場合は応急処置として足を冷却しますが、変形性膝関節症の痛みには保温、と覚えておきましょう。
また、夏場にエアコンをつけたまま就寝すると膝周りが冷えてしまい、血液循環が悪くなってしまいます。朝起きがけが一番膝が痛いという方はエアコンが原因で膝が冷えている可能性があるので、十分注意が必要です。
必ず長ズボンで寝ることと柔らかめのサポーター(締め付けない程度の保温性のあるもの)を膝につけて寝て下さい。
畳での寝起き、正座、和式トイレ、などの日本式の生活は、膝関節や股関節に負担がかかりがちです。ベッドでの寝起き、椅子での食事、洋式トイレなど、生活を洋式に切り替えることで膝関節や股関節にかかる負担を減らすことができます。
また長時間、立ちっぱなしでいることも膝に良くありません。可能であれば、料理をする時は椅子に腰かけて、洗濯物を畳む時は椅子に座り、テーブルの上で行うようにしましょう。
変形性関節症の治療は、まず手術以外の保存療法から始め、症状の改善が見られない場合は手術療法を検討します。
どちら場合にも、関節症状を悪化させないため、労働量の調節・運動・体重コントロールなど、日常生活にも気をつけることが大切です。
保存療法には、運動療法、薬物療法(鎮痛剤、ヒアルロン酸注射など)、装具療法(サポーターなど)があります。手術療法には、人工関節置換術などがあります。
放っておかないこと、そして、お医者さんと一緒に治療していく気持ちが大切です。
関節の機能を維持するために、ストレッチ運動と関節周囲の筋力トレーニングを行います。とくにシニアに多い変形性膝関節症では、太ももの前側の筋肉など、膝関節周囲の筋肉をトレーニングすることが重要です。筋肉を鍛えることにより、関節への負担や衝撃が和らぎ、症状の軽減や悪化予防につながります。スクワット運動など、体重をかけて曲げ伸ばしする運動は逆効果なので気を付けましょう。
医師や理学療法士からアドバイスを受け、自分に合った方法で行ってください。運動療法はすぐに痛みに対して効果が出るわけではありません。焦らず長い目で、トレーニングを続けることが大切です。
変形性関節症の装具療法には、サポーターやインソール、杖などがあります。関節の安定化や負担の軽減、痛みの緩和、歩行の安定性向上などの効果が期待できます。
また、医療用の膝サポーターには、保険適用のものと、自費となるものがあります。
整形外科や病院で処方される膝サポーターは、医療用として国から認められているものが多いのですが、市販のサポーターは、医療機器としての認可を受けていないものもあるので、保険適用のサポーターを利用したい方は、医師に確認してください。
関節の炎症を抑え、痛みをとるための消炎鎮痛剤や、関節のすべりを良くするヒアルロン酸やステロイド剤の関節内注射などを行います。
また、近年では再生医療でも変形性膝関節症は治療ができるようになりました。治療の選択肢が広がっています。
変形性関節症の再生医療には、関節内の炎症を抑えたり、傷んだ組織を修復したりする治療法があります。
保存療法と手術療法の間の「第3の治療法」として注目されています。
再生医療とは、人間が本来持つ「自己治癒力」を活用し、ひざ等を治療する最先端の医療です。薬物療法やヒアルロン酸注射などの保存療法は、痛みを一時的に緩和する程度で、症状の進行を止めることはできません。
一方、再生医療は、損傷した組織を再生させることで、痛みを改善し、症状の進行を遅らせる可能性があります。
ただし、現在、変形性膝関節症に対する再生医療(PRP療法、APS療法、幹細胞治療など)は、原則として保険適用外で、自由診療として扱われます。
治療費は、医療機関や治療法によって異なり高額になる傾向がありますが、高額療養費制度や限度額適用認定証の利用、医療費控除で税金の還付を受けることなども可能な場合があります。
再生医療は関節の痛みに悩む多くの方に希望をもたらす治療法ですが、種類や費用は医療機関によって異なりますので、事前に確認することが大切です。

『シン・整形外科 綱島』は、横浜、綱島駅徒歩1分にある整形外科・リハビリ科クリニックです。
一般外来での痛みの治療から、リハビリテーション、そして再生医療や骨粗鬆症等の専門外来まで幅広く診療を行っています。
膝を始め、肩や股関節、足関節までの診療を行っていて、なかなか治らない慢性的なお痛みがある方、手術を避けて日帰りで治療をされたい方、仕事を長期でお休みできないを方を中心に、再生医療での治療も提案しているクリニックです。痛みは早期診断と早期治療が重要。
まずは整形外科専門医による診察を受けてきませんか?

ひざ関節症クリニックは北海道から九州の全国15の拠点で、ひざ痛の原因として特に多い、変形性膝関節症の治療を中心とした診療を行っています。
中でも注力するのが、再生医療を始めとする先進的な治療法です。
セカンドオピニオンにも対応しており、同様に詳しく診断し、再生医療に限らず、適した治療法を提案してくれます。
完全予約制なので相談時間にも余裕をもって診断してくれます。
「効果が得られない」ということの無いよう事前のMRI検査を必須とし適応診断をしてくれるので、安心です。また、日本整形外科学会認定の専門医だけが診療にあたります。
膝の痛みに悩まない毎日を取り戻すため、まずはお気軽にご相談してみてはいかがでしょうか。
変形性関節症の手術療法には、骨切り術や人工関節置換術などがあります。
手術の適応や種類は、患者さんの年齢や活動量、関節の状態などによって異なり、手術の効果を十分に出すためには、手術後数週間〜数ヶ月間、しっかりとリハビリを行うことが大切です。

年をとってから関節が痛まないよう、若いころから脂肪を落とし、筋肉をつけるように努力しましょう。
また、初期症状であれば症状が悪化してしまうことを防ぐこともでき、関節に痛みがある人や違和感がある人は病院で診断してもらうとともに予防方法も行うことをおすすめします。
特に、変形性膝関節症を予防するためには、膝の周囲の筋肉、とくに太ももの前にある大腿四頭筋を鍛えることが重要です。膝関節の動きをよくするため、膝のストレッチングも大切です。
そして、食事内容を見直すことで変形性関節症の痛みを軽減できると期待されています。栄養バランスが整った食事を摂取することも大切ですが、軟骨を形成しているグルコサミンが多く含まれている食材を摂取してみてください。
グルコサミンが変形性関節症に対してはっきりとした効果を示したというデータは残念ながらありませんが、痛みを軽減できる可能性があるといわれています。
食事内容を変えるだけでも症状をやわらげられる可能性があり、予防策としては有効的です。